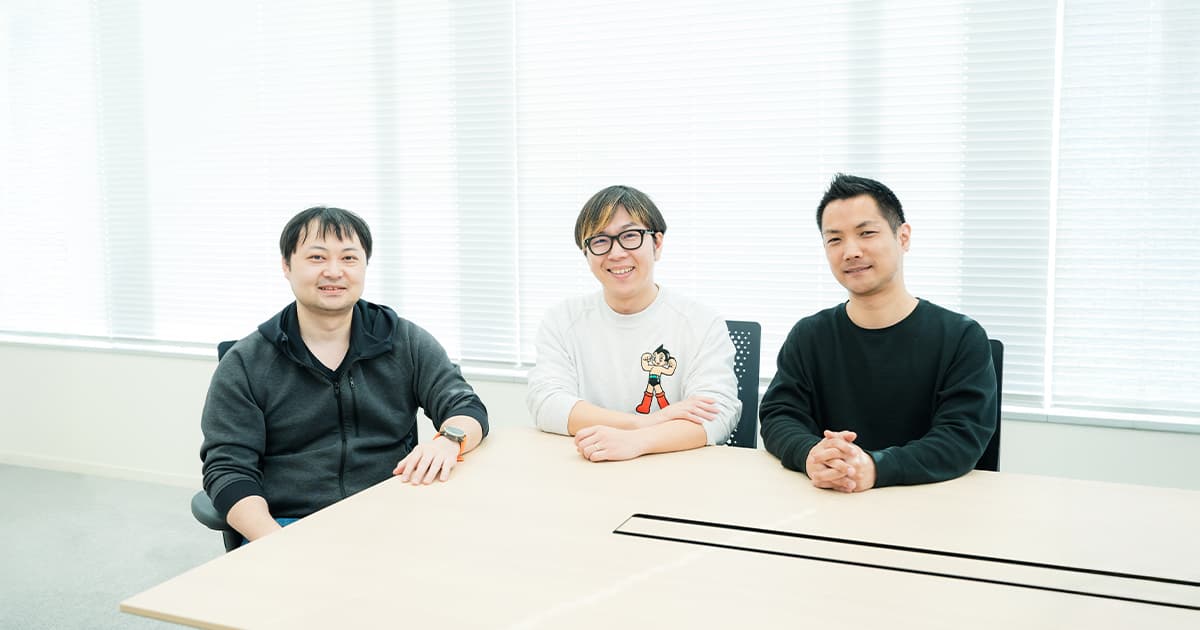AI記事要約
過渡期を迎えている国内のゲーム市場。生成AIの急速な発展や海外企業の台頭、プラットフォームの多様化などの影響を受け、新規タイトルの成長・拡大はますます難易度が上がっています。そうした中、コロプラでは成熟した市場を突破する鍵として「位置ゲー」、「AI活用」、「海外展開」を掲げ、技術の積み重ねを強みに新しいUXの創造に挑んでいます。
今回、ゲーム事業を牽引する取締役の坂本佑と執行役員の角田亮二の対談を実施。ゲーム業界の現状や展望、生成AIを「おもしろいゲーム体験」に発展させる独自の取り組み、ウェアラブルデバイス時代を見据えた未来構想まで、エンターテインメントで日常をより楽しくするコロプラの戦略をたっぷりと語り合ってもらいました。

取締役 上席執行役員 CPO エンターテインメント本部 本部長 兼 マーケティング戦略室 室長
- 坂本 佑
大手ゲームメーカーにエンジニアとして新卒入社し、プランナーに転向。アミューズメント系のゲーム開発に携わった後、モバイルゲームの開発に従事。コロプラには、2013年に中途入社。
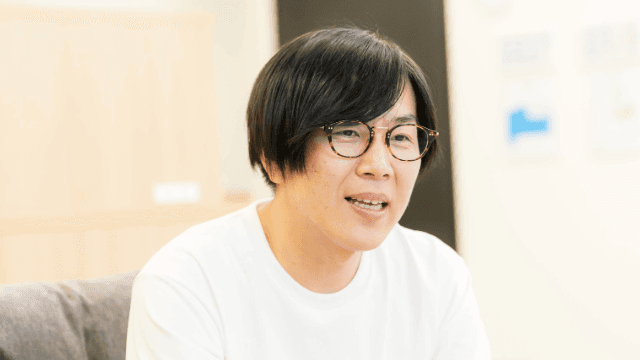
執行役員 エンターテインメント本部副本部長 リードクリエイター
- 角田 亮二
映像制作会社を経て、2012年6月にコロプラに入社。『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』、『白猫プロジェクト』など複数タイトルのディレクターとして開発に携わり、現在は新規開発タイトルのディレクターなどを務める。
煮詰まりつつある市場をどう打破するか
ゲーム事業を管掌している坂本さんと角田さん。お二人は役割をどのように分担しているのですか?

僕はCPO(Chief Product Officer)として、「位置ゲー」を中心にゲーム事業をとりまとめています。加えて、市場創造型マーケティングを実現すべく、マーケティング領域も管掌しています。

私は坂本さんの配下におり、『白猫プロジェクト』や『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』といった自社IPのゲーム開発・運営、IP活用を主に担当しています。また、先端技術を使った新規タイトルの開発にも携わっており、最近では画像生成AIを活用したローグライクゲーム『神魔狩りのツクヨミ』を担当し、2025年5月にリリースしました。現在はこのゲームを世の中にさらに広めるべく、取り組みを進めています。
ゲーム業界は今、大きな過渡期を迎えています。お二人は最近の市況感をどのように捉えていますか?

ゲーム市場は依然として成長中です。しかし、その成長を支えているのは長く人気を博してきたIPで、新規のタイトルやIPで利益を生み出すことは難易度が高いのが現状です。市場はすでに煮詰まってしまっており、あらゆるプラットフォームが厳しい状況に置かれていると言えます。

ただ、そうした中でも、Steamはかなり例外的なプラットフォームですよね。

そうですね。Steamでは、小規模なデベロッパーが開発した新規のインディゲームが爆発的なヒットを飛ばすなど、成功事例が相次いでいます。しかし、そうした輝かしい成功の裏側にはSteamならではの多産多死な環境があり、年間に1万本以上のタイトルがリリースされるうち、商業的に成功しているタイトルの割合は高くないという状況です。
これはモバイルゲーム市場にも共通する傾向で、特に昨今はプラットフォーム全体の成熟に伴い、新規タイトルが収益を上げるハードルは一層高くなっています。ダウンロード数や初動のインパクトだけでは生き残れず、持続的な運営力や独自性が強く求められるフェーズに入っていると感じます。
そうした市況感の中、コロプラのゲーム事業ではどのようなアクションを起こしていくのでしょうか。

ひとつは、「位置ゲー」を追求していくことです。現実世界での移動がゲーム内容に影響する位置ゲーは、モバイルだからこそ実現できる遊び方。そのため、リリースしたタイトルのヒット率が高くなりやすいという特徴があります。また、日々の習慣の中にゲームが組み込まれることから、一度遊んでもらえると長期的に支持される作品になりやすい。昨今の厳しい市場の中でも、ユニークなポジションを狙えるジャンルだと考えています。

自社IPの観点で言えば、『白猫プロジェクト』などの長期運用タイトルは、今もなお多くのユーザーさまに支持していただいています。既存IPに関しては、今後も「エンターテインメントとしてより良い価値をユーザーさまに届けていくこと」を徹底していくつもりです。

あとは、やはり「AI」ですよね。

そうですね。コロプラの「最新テクノロジーを用いてゲーム開発に挑むカルチャー」をベースに、「AIを使った新しい体験の創造」にも前のめりにチャレンジしていきたいです。AIを新しいエンターテインメントに昇華させられれば、昨今の停滞感ある市場に風穴を開けられると思います。

結局のところ、誰もが驚くような未知の体験をどこも生み出せていないから、市場の煮詰まり感が出ているのだと思います。各プラットフォームで実現できる“遊び”が一通り出そろい、どのタイトルを見ても「大体こんな感じだろうな」と想像できてしまう。そうした状況を打破するためには、ユーザーさまに「新しいかもしれない」と期待をかけていただけるようなゲームを作るしかありません。生成AIには、そうした“全く新しい体験”を生み出せる可能性がある。だからこそ、我々は今、AI活用に力を入れているのです。
中期経営方針に「新しいUXの提供」という言葉が書かれているのは、今お話しいただいたような背景も影響していますか?

おっしゃる通りです。新しいものを無作為に作ってもなかなかユーザーさまに届かない市況感だからこそ、「どういう体験、ゲームであれば受け入れてもらえるのか」「どのような市場であれば、コロプラの強みを生かしたゲームを届けられるのか」を突き詰めて考えていった結果、「新しいUXの提供」を始めとして「海外市場への積極展開」「国内IPの活用」を加えた3軸を中期経営方針として据えることにしました。

技術を積み上げ、未来への可能性を拓く
コロプラのゲーム開発における強みは、どこにあると思いますか?

技術を積み上げてきた点にあると思います。ゲーム会社では、各プロダクトに何らかの連続性を持たせる戦略をとっているところが多いですが、そのほとんどは強いIPやジャンルでシリーズ作品を開発するパターンです。技術的な連続性を意識している企業は、そこまで多くはありません。その点、コロプラでは、一つひとつの開発タイトルに技術的なチャレンジを盛り込んでおり、作品を重ねるごとに、会社として制作できるゲームの幅が広がってきています。

例えば、『黒猫のウィズ』が誕生するまでには、ネイティブゲームの開発に多数チャレンジした歴史がありました。また、『フェスバ+』で導入した「ロールバックネットコード(※)」も、『白猫テニス』での技術的チャレンジがあった結果、実現させることができました。

位置ゲーも、『コロニーな生活』があったからこそ、『ドラクエウォーク』などが実現できています。シリーズ作品ではないタイトル群でも、毎回必ず技術的なチャレンジをすることで、コロプラ全体としてみると、オールレンジに技術が積み上がっている状態を作れているのです。これまでできなかったことを、次のタイトルでは何とかして実現させていく。最高の体験価値を求め、技術を追求する姿勢は、最大のコロプラらしさだと思います。
※ロールバックネットコード:格闘ゲームなどのリアルタイム性が求められるオンラインゲームにおいて、プレイヤー間の遅延を解消し、同期をとるための技術。
技術の追求という観点で、「ゲーム開発における生成AIの活用状況」についても教えてください。

最初はクリエイター陣の中にも、AIに対する心理的な抵抗感があり、浸透は遅めでした。しかし、あくまで「ツール」としてのAI活用を地道に進めていく中で、実際に使ってもらいながら、AIがやったほうがいいこと、人じゃないとできないことの線引きが見えてきました。現在は、AIと職人技の両立ができていて、それに合わせて社内のルールも柔軟にアップデートしているところです。

AIに取り組み始めたのは遅いほうだと思っていたのですが、コロプラの取り組みは業界内でもだいぶ進んでいますよね。
『神魔狩りのツクヨミ』では、カードのイラストを画像生成AIに描かせることで、自分だけのカードが手に入るゲーム性が話題となりました。「AI×ローグライクゲーム」の未来像をひとつ提案できたタイトルになったように思います。

『神ツク』では、AIによって出てきたアウトプットをユーザーさま同士で評価し合う仕組みも実装させました。また、AIが作成したイラストは、自分のプレイ内容に紐づいているからこそ唯一無二性が高く、多くのユーザーさまが自分の引き当てたカードに愛着を持ってくださっています。そうした「ゲーム内での新たな体験」をAIを用いて作れたことは大きな意味があり、今後も単にAIを使うのではなく、AIを「おもしろいゲーム体験」に昇華させることに注力していきたいと思っています。

最近、会長の馬場の発案で、生成AIと一緒に遊ぶ体験を「生成ゲーム」と名づけました。生成AIとさまざまな技術の掛け合わせはもちろん、自社や他社のIPを活用した生成ゲームの開発も検討しています。スマートフォンゲームだけでなく、PCゲームなどでの展開も検討しており、ゲームファンの方々にも、日頃あまりゲームに触れない方々にも「新しい」「おもしろい」と思っていただけるようなゲームをお届けしていきたいと考えています。
IPの持つ魅力を最大限活かすゲームづくり
IP活用で大切にしていることを教えてください。

「IPの持つ根源的な魅力や特性を活かすこと」を意識しています。

IPの根本的な価値を守り、揺るがさないようにすることは、開発に携わるメンバー全員が思っていることなのではないでしょうか。

例えば、2024年8月にサービスを開始したスマートフォンゲーム『フェスバ+』は、コロプラの開発した『白猫プロジェクト』とMIXIの開発した『モンスターストライク(以下、モンスト)』をコラボさせたタイトルです。モンストとタッグを組むことに決めたのは、お互いのコンセプトがマッチし、シナジー効果を生み出せると感じたから。『白猫プロジェクト』はもともと「やろうよ!」がキャッチコピーとなっていた時代もあるように、誰かと一緒にプレイすることがコンセプトのゲームです。モンストも友達と一緒に遊ぶマルチプレイのイメージが強いタイトルですから、『フェスバ+』で実現したかったGvG(guild versus guild)ジャンルのゲームでお互いのIPに相乗効果があると考えたのです。結果的に『フェスバ+』は、令和時代の新しい「やろうよ!」を提供できたのではないかと思っています。

中国をはじめとした海外発パブリッシャーの存在感が増している中、日本のゲーム産業をさらに盛り上げるべくMIXI社と同じ目線で協業できるのは、とてもありがたいことだと感じます。また、『フェスバ+』だけでなく、『異世界∞異世界』も各IPの魅力を掛け合わせて新たな価値を生み出せた事例のひとつだと思っています。アニメIPを高頻度で無限にリリースしていくようなゲームは、古今東西どこを見ても、他に例がないのではないでしょうか。コロプラらしさが出ているタイトルだと思います。
コロプラには、『ドラゴンクエストウォーク』など他社IPをもとに開発したゲームもあります。

他社IPをお借りする場合であっても、基本的な考え方は自社IPを活用する際と一緒です。そのIPを愛している人が、IPの持つどのような価値や特徴を大切にしているのか。なぜ、そのIPが好きなのか。そういった点を深く掘り下げて考え、IPの魅力を最も活かせるゲームを企画していきます。『ドラクエウォーク』であれば、ドラクエの本質は「冒険」だというところから、位置ゲーとの相性が良いのではないかと、スクウェア・エニックス社とともに考えました。日常を自らが冒険者となって冒険するコンセプトで開発し、完成したのが、あのゲームなんです。

人気IPだから活用する、ということではないんですよね。IPの魅力と、コロプラだからこそ作れるゲームの体験価値を掛け合わせることに大きな意義があると考えています。
グローバルを見据えたゲーム展開の戦略とは
海外市場への展開について、コロプラとして現在考えていることを教えてください。

北米圏への進出に関しては、やはり市場が顕在化している「位置ゲー」が鍵になると考えています。アジア各国では、位置情報取得に関する政府の規制が厳しかったり、国民に使われているインターネットサービスや地図アプリがその国独自のものだったりして、実は位置ゲーの展開が難しいんです。一方、北米では『ポケモンGO』などが開発され、人気を博しています。すでに大きな市場が存在していますから、我々の技術やノウハウを使って、何らかの結果を残せるのではないかと思っています。

市場の大きさで言えば、中国を含むアジア圏も魅力的です。特にアジアの国々は、日本発のカルチャーやビジュアル表現が受け入れられやすいですし、なにより日本のIPが人気です。PvP(Player vs Player)やSLG(シミュレーションゲーム)といった日本とは異なるゲームトレンドを押さえつつ、日本発でしかできない取り組みで市場に食い込んでいければと考えています。

アジア圏には、金子一馬さんのファンも多くいらっしゃいます。金子さんがコンセプトプランナーを務めた『神ツク』も、東南アジアで一部反響が見られており、海外市場では、著名なクリエイターや人気IPとのコラボレーションも効果的なのかもしれません。今後もさまざまな知見を蓄えながら、海外展開を加速させていきたいと思っています。

さらに長期目線では、2032年までに中国と同等の市場規模になると予測されているインド市場にも目を向けておきたいところです。業界では、すでにインド市場に可能性を見出し、動き出している企業もあります。コロプラとしても、インド市場に対して提供できるものをリサーチし、検討していけたらと考えています。
海外では、Steamなど日本とは異なるゲームプラットフォームが主流なケースも多いですよね。

おっしゃる通り、SteamなどのPCゲームプラットフォームはグローバルに開かれており、中国や北米、ロシアなど多様な国のユーザーが利用しています。Steamのような月に何千、何万本ものタイトルがリリースされるプラットフォームを制するためには、アーティスティックなビジュアルにこだわったり、脱出ゲームやメトロイドヴァニアなどの独自の人気ジャンルでゲームを開発したりと、工夫を凝らす必要があります。また、1本あたり1,000円以下の「安く、おもしろいゲーム」が好まれる傾向もあるため、会社としては事業性なども検討しなければなりません。グローバルを見据えたPCゲーム市場への進出については、しっかりと策を練った上で進めていかなければならないと感じています。
コンシューマーゲームでの展開はいかがでしょうか。

実は今、具体的なプロジェクトを進めているところです。というのも、いろいろと調査をしてみると、スマートフォンゲームのユーザー層とCSのユーザー層にも重なり合う部分が多いことが分かりました。これまで培ったノウハウや資産を活かし面白い取組ができるのでは?と考えています。

コンシューマーゲームを開発する際、コロプラとして提供する体験価値はどのようなものになるのでしょうか。

コンシューマーゲームでしか実現できない「保存性」に着目し、ゲームを作りたいと考えています。スマートフォンゲームは、良くも悪くも進化し続けるもの。そのため、ユーザーさまが「楽しい」「好き」と感じてくださった体験が、数年後には残っていないこともあり得ます。タイトルの持つおもしろさを何年経っても追体験できるのは、コンシューマーゲームならでは。自社IPのゲーム体験をコンシューマーゲームとして保存することで、多くのユーザーさまに新たな価値をお届けできるのではないかと考えています。
長期運用タイトルでは「新しい挑戦」を欠かさない
11周年を迎える『白猫プロジェクト』など、コロプラには長期運用タイトルもあります。長きにわたって愛されるタイトルを運営できている秘訣は、どのようなところにあるのでしょうか。

ポイントはやはり、既存タイトルであっても「新しい要素」を常に取り入れ続けていることだと思います。

そうかもしれないですね。作り手として、ユーザーさまの想像を一歩超えたものを作り続けようと意識しているからこそ、10年を超える長期タイトルが生まれているのだと思います。直近では、『黒猫のウィズ』のリリース11周年イベントとして「クイズラッシュ」という独自の放置型育成コンテンツを開発し、追加したのですが、結果として既存ユーザーを楽しませるだけでなく、新規ユーザーの獲得にもつながりました。各タイトルの運用トップであるディレクターに大きな裁量を持たせており、ユーザーさまにとって最適かつ新しい体験を届けられる運用体制になっているのも、長期運用タイトルの誕生に大きく影響しているのかもしれません。

人間は実は我々が思っている以上に現状維持を望んでしまう生き物ですが、それでもただ同じものばかりを与えられ続けていると、いずれ自覚の有無にかかわらず“飽き”が生じてくるものです。そこに対して、我々は常に新しい刺激を入れようと工夫し続けている。もちろん、すべての施策がユーザーさまに評価していただけるわけではありませんが、それでも挑戦をやめないからこそ、多くのユーザーさまにタイトルを愛し続けていただくことができているのだと考えています。
日常を彩る新しいゲーム体験の開発を目指して
5~10年後のゲーム業界を見通し、今後の展望をお聞かせください。

実はつい最近、角田さんとゲーム業界の未来について話していたところなのですが、今後は「ウェアラブルデバイス」の領域が伸びていくのではないかと考えています。コロプラは業界に先駆けてXR領域に進出していましたが、いよいよ市場として拡大していくフェーズなのではないかと。特にAI技術の発展で画像・映像処理の性能が格段に上がった「スマートグラス」は、コロプラが目指すミッションやビジョンの実現に限りなく近づいたゲーム開発を叶えられるのではないかと思っていて。
我々は、ミッションとして「“Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」という言葉を掲げています。『コロニーな生活』という位置ゲーで、多くのユーザーさまの日常生活を彩り豊かなものにしてきたように、これからもさまざまなゲーム体験を通じて、多くの方の日常生活をよりおもしろく豊かなものへと変えるお手伝いをしていきたいと考えているんです。だからこそコロプラでは、従来の「画面の中で楽しむゲーム」だけではなく、『Brilliantcrypto』のようなゲーム世界で得たものが現実世界の価値になるPlay to Earnゲームや、ゲームキャラクターとリアルタイムにコミュニケーションがとれる「LPG(Live Playing Game)」ジャンルのゲームの開発、XRでの体験創造などに挑戦してきました。
「現実を拡張し、新たな体験をつくること」にこだわり、これほどまでに多ジャンルで挑戦を続けてきた企業はほかにないと自負しています。だからこそ、スマートグラスが普及した暁には、これまでの数々の挑戦が1本の線となってつながり、現実世界と境目なく遊べる新しいゲームを作れるかもしれません。日々の暮らしがゲームの世界とつながり、キャラクターとコミュニケーションをとったり、お金を稼いだり、散歩が位置ゲーとリンクして遊べたり……、そんな風に生活のすべてがゲームになる未来も実現できる可能性があります。10年後、そうした全く新しい世界観を実現できるように、これからもゲームづくりに挑んでいきたいです。
これまでの価値観を捨て、変化に柔軟に対応できるか
今後、どのような方にコロプラの一員として参画してほしいですか?

これまでも各所でお伝えしてきましたが、常に新しい体験をつくり続けているコロプラでは、「素直さ」のある方、つまり変化に対して柔軟に対応できる方がマッチしているように思います。生成AIが急速に発展している現在、変化への順応性はますます重要な資質になっていると感じます。これまでの経験やスキルをすべて捨てることもいとわず、世の中の変化に臨機応変に向き合い、新しい物事を積極的に学べる。これからのゲーム産業では、そうしたマインドや姿勢が求められるように思います。

同感です。経験やスキルの比重はかなり下がってきていますよね。

生半可なスキルでは、AIに太刀打ちできませんからね。
コロプラでは今後、社内でAI活用を進め、人間のリソースを「ゲームをよりおもしろくすること」に使っていきたいという方針があります。その観点から考えると、今後の採用活動において、思考力や創造性の高さは必須の要件となるのでしょうか?

生成AIはどこまでいっても「自己増幅装置」でしかないので、思考力や創造力の高さはあった方が望ましいのは確かです。ただ、これまで以上に求められる、とは断言できないですね。というのも、思考力や創造力といった領域においても生成AIの進化は目覚ましく、必要に応じて生成AIに考えてもらうことも必要になってくると考えるからです。

人間が考える凡そのクリエイティブは、生成AIでも考えられるようになってきたと感じます。AIと正しくコミュニケーションがとれれば、人間が作ったものに引けを取らないもしくは、それを超えてくるアウトプットが出てくるようになってきました。

角田さんは最近、すごいですよね。AIでいろいろなものを作っていて。

僕はもともと映像制作を生業にしていたのですが、最近はAIが効率的なスクリプトやアイデアや原案をバンバン出してくれるようになったので、当時よりもはるかに速いスピードでアウトプットできている実感があります。空いた時間で他のこともできるので、AIにより出来ることが拡張したと感じています。

AIで自分の持てるものを最大限に増幅させて仕事をしている角田さんの姿を見ていると、やはりインプットし続けることは大切だなと感じます。時代の空気や最近のトレンド、進化した技術、古今東西の文化や作品……これまで触れてきたものが自分の中でセンスや感覚として育ち、それがAIによってより一層強化されて、仕事のアウトプットとして効率的に出力される世界になりつつあるんです。だからこそ、従来の価値観に固執することなく、新しい物事に貪欲であってほしい。意欲的にアンテナを広げて、積極的に新しい情報や体験を得に行く方にぜひ仲間となっていただけたらと思います。

AIの躍進で、自分自身をうまくモチベートできることも重要になってきている気がします。ゲーム業界の市況感はとても厳しいですが、その中でも自分にポジティブに働きかけて、前向きに仕事ができるかどうか。そして、他者とのコミュニケーションでも、お互いにポジティブな影響を与えあえるような言葉の使い方や話し方ができるかどうか。そうした点が、今後より一層求められるように思います。
※位置ゲーは株式会社コロプラの登録商標です。



.png&w=3840&q=75)